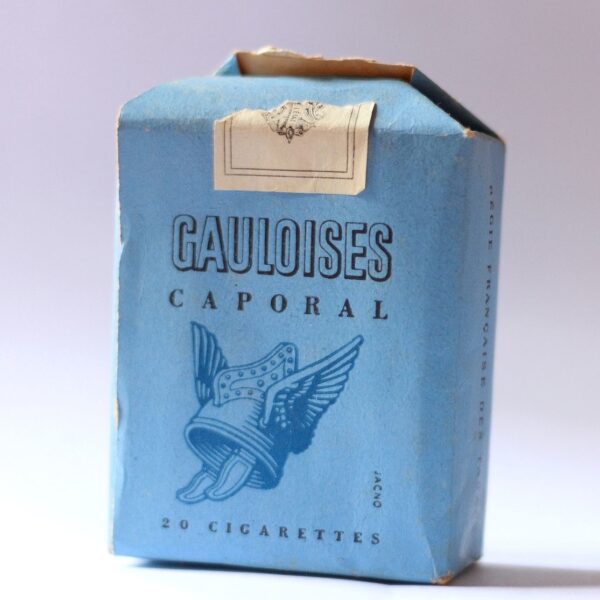1985年発行の冊子「街角から」。表紙の絵は大沢昌助の作品。
本の整理をしていたら、昔の冊子が出てきました。
インドネシアへ旅行したのが、1984年で私が33、4歳頃のことだったのかしら。「街角から」のために書いた文章を久しぶりに読んで、その頃はこんなことを考えていたんだとあらためて思う四月。若い日の記録と備忘のためにここに載せておくことにしました。

「南の島で」 文:内田あぐり
異国への短い旅は、はっきりとした目的や期待も持たず、むしろ空白に近い状態で旅する方が好ましいようです。そうした淡々とした気持ちで旅先を歩いてる私の前に突如として異形の光景や文化があらわれたとき、その意外性ゆえに驚きと感動はよりいっそう大きなものとなって私の脳裏に侵入してくるのです。生きていくことの道のりが決して計算されることのできない様々な遭遇に満ち満ちているように。
去年の暮れに絵描き仲間に誘われて旅をしたインドネシア行きも常夏の国へ泳ぎに行こうかという安易な動機からでした。友人達は大きなスケッチブックと画材やらで旅行鞄を膨らませているのに、私といえば小さなスケッチブック1冊のみ、そしてかばんの中味は食料品ではちきれそうという実に怠慢な旅立ち。案の定、現地に着くや否や友人達はスケッチブックを抱えて近辺へと繰り出して行ったのです。とにかく、猛烈な暑さの中に原色の風景、そして官能的な匂いを漂わせる赤や白の花々、その花を髪に飾り街を往来するコケティッシュな老若男女、そこは極楽鳥でも飛び交うような日常を超越した光景でした。そうした現実離れをした空間の中で、つい何時間か前まで東京でしていた絵の仕事を引きずりながら、この楽園での短い滞在はとても過ごすことができないという罪悪感にも似た気持ちを抱くのも不思議ではないくらいでした。
島に着いた夜、すでに12時をまわっていたでしょうか、あまりの蒸し暑さに眠ることのできなかった私は、人気のないホテルのプールに飛び込み南十字星を見ながら泳ぎ、ビールを飲んではまた泳ぎ、ひたすら暑い闇の中で泳いだのです。そうすることで体の中にずっしりと蓄積された塵のような日々の重みを水中に放出するかの如く、すっかり体力を使い果たした私の体はまるで浮遊してしまうかのように空っぽになってしまったのでした。
バロン、ケチャック、レゴンダンスと炎天下の中を連日様々な民俗芸能を見て歩いたのですが、島の歴史的背景のもとで繰り広げられる肉体と精神が一体化した豊饒な踊りは、エナジーの中に崇高な美しさを感じるものばかりでした。しかし、絵描きとして一人の若い踊り子のきらびやかな衣装をつけた完璧にまで整った姿態を見ると、どこか京都の舞妓のイメージと重なってしまい、彼女達の存在が見せるためのものにある、伝統という衣をまとった型通りの人工美としてしか映らなかったのです。むしろ私の気をひたのは、節くれだった指を持つ果物や野菜を売る市場の女達、街中で何を思っているのか空を視つめて大地にうずくまっている男と女、金持ちの旅行者に群がる若い少女のような客引き、田園地帯の小さな寺院でひたすら祈りを捧げる老女達なのでした。
そうした私の意識の内に入り込んできた人々を素朴な気持ちから旅の記録にと思いいく枚かスケッチはしたものの、あくまでもそれらは私がしていく旅の断章にすぎず、その刹那に鉛筆で描かれただけの女のカタチが旅人のかかわり合いをとおしてスケッチブックに記されているのです。
絵を描くものの中には異国へ赴き、その風景や人間を取材し自分の作品にそれらを登場させることが多いようですが、ごく一部の作品を除いては、ほとんどがお土産品的発想のようで、いま流行っている中国やインドを描いた作品の多くもそうした現象の極致をいくものなのでしょう。混沌とした社会の中で、なおかつ過剰な絵の氾濫の故に、外へと描く対象物を求めざるをえないのも無理はないのかもしれません。しかしながら現代社会の中で、超先進国と言われている日本を担わなければならないはずのアーティストたちが、その混沌をも受け止めてる事なく異国の文化や風俗を様々なテクニックを駆使して模倣する様は実に情けない事としか私の目には映らないのです。一つの表層として、私はこの現象を捉えているのですが、それが称賛されている昨今、日本人のオリジナリティーはそして美意識はいったいどうなってしまったのだろうかと、危機感さえも抱くのです。
そうした現実を無視するかの如く、私の過ごした南の島は絵描きなどには太刀打ちできない深い信仰と眩しいほどの原色の光景を誇示していたのでした。
楽園の夜は鳥の泣き叫ぶ中、亜熱帯の木々に覆われて点在する家々に薄暗い灯りがともり、人々はベランダにある籐椅子の上で長く深い闇の刻を過ごします。昼間のどこまでも明るい健康的な表情は一変して花々は官能的な匂いをよりいっそう強く発散させ、淫靡な空気を漂わせるようです。昼と夜がこうも豹変してしまうのは、南の島が持つ特有の気候と風土とそれに培われた人間性によるものなのでしょう。
ふとタヒチをこよなく愛したゴーギャンの絵を思い浮かべ、たった今から私のすべてが瑠璃色の楽園の中にどっぷりと浸ることができたらと思うのでした。
(街角からNo.4, 1985年発行)
「街角から」の見出しの絵、Van Dongenのドローイング。

文章の終わりに、私のリトグラフ「ふたり」